-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
2025年12月 日 月 火 水 木 金 土 « 10月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
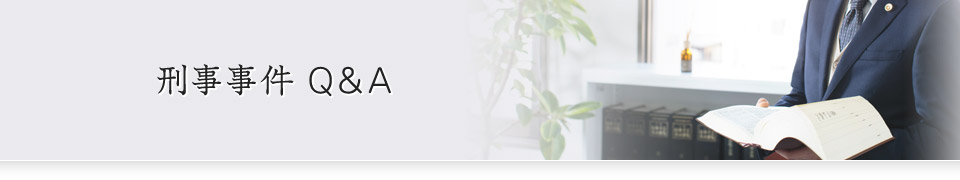
ニュースで頻繁に耳にする「●●は、懲役●年執行猶予●年に処せられました…」
「懲役」とは刑務所に入って、役務を行わなければならない刑罰です。
「執行猶予」とは、「執行猶予期間内に、他の犯罪を起こさなければ、判決の効力が発生しないことになる」という制度です。
つまり、懲役1年6月執行猶予3年の判決が下されたとしますと、これは「刑罰としては3年の懲役としますが、直ちにこれを執行しません。これから3年間犯罪を犯さなければその刑罰はなかったことにしますよ」という意味なのです。
つまり、執行猶予判決は、判決後も通常の生活を送ることができるのです。
ですので、判決で執行猶予が付されるかどうかは、被告人の今後の人生にとって大きな意味を持つのです。
したがって、弁護人は、執行猶予が付される可能性がある事案については、裁判官に様々な観点から情状酌量を求め、寛大な判決(執行猶予付きの判決)を求めるのです。